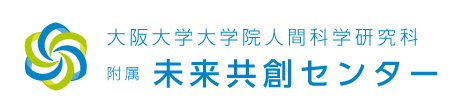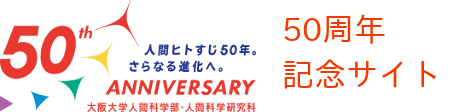「災害レジリエンスを高めるための基盤調査」報告会
ドキュメントダウンロード
❖ 概要
大阪大学大学院人間科学研究科は、12 月 20 日(金)に「災害レジリエンスを高めるための基盤調査」報告会を開催します。
人間科学研究科 稲場圭信教授、川端亮教授らのグループは、研究プロジェクト「災害レジリエンスを高めるための基盤調査~多様性によるイノベーション・インパクト~」において、2024 年 8 月~10 月の期間に、基礎自治体の防災関連システムに関して初めての全国調査を行いました。また、コロナ禍前の2019 年 12 月~2020 年 2 月に実施した「自治体と宗教施設・団体との災害時協力に関する調査」(令和元年調査)と同様の調査も実施しました。
今回の報告会では調査結果の報告を行うとともに、東日本大震災、熊本地震、令和6年能登半島地震の経験も含めて、「全国ではどれほどの宗教施設が避難所指定されているのか?」「自治体と宗教施設の災害時協力は進んでいるのか?」「基礎自治体の防災関連システムの現状と課題は?」というような点についてお話をしたいと考えています。当日は、未来共生災害救援マップ(災救マップ)のデモンストレーションも行います。
つきましては、ぜひ当日のご取材にお越しいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
❖ 記者発表
「災害レジリエンスを高めるための基盤調査」報告会
【日 時】 12 月 20 日(金) 11:00 ~ 12:00
【場 所】 大阪大学大学院人間科学研究科本館 5 階キャノピーホール(吹田キャンパス)
【登壇者】 研究代表者:稲場圭信(大阪大学大学院人間科学研究科教授)
研究分担者:川端 亮(大阪大学大学院人間科学研究科教授)
(協力者:医学研究科高度救命救急センターDMAT:織田順教授・入澤太郎講師・酒井智彦助教、情報科学研究科:山口弘純教授)
【内 容】
① 自治体の防災システムの現状と課題に関する調査報告
② 自治体と宗教施設・団体との災害時協力に関する調査報告
③ 災救マップのデモンストレーション、質疑応答
❖ 「何故、行うのか?」本企画の背景:時代の要請への応答
気候変動の影響や大地震を受けて、レジリエントな社会の構築が求められています。しかしながら、国や自治体レベルの災害対策は十分とは言えず、大災害が発生するたびに避難所が不足し、情報の集約と共有の遅れから救命と被災者支援対応も遅れるという課題を抱えています。これは、南海トラフ地震などの大災害の継続が予想される中で大きな社会課題です。
❖ 調査結果の概要
今回、この課題の現状を正確に把握するため、①自治体の防災システムの現状と課題に関する初めての全国調査 ②自治体と宗教施設・団体との災害時協力に関する調査 の2つの調査を行いました。
①自治体の防災システムの現状と課題に関する初めての全国調査
全国 1741 自治体に調査票を送付し、1143 自治体から回答がありました(回収率 65.7%)。国や都道府県のシステムを使用している基礎自治体の約 6 割以上が「システム導入のコストやランニングコストが高い」と回答し、5 割以上が「職員のマンパワー不足でシステムを運用するのが困難」という回答していました。また、「避難者の既往症や薬の情報を把握できない」という回答が 4 割以上に上りました。今後の我が国における防災・減災システムの構築に資する貴重なデータを収集することができました。産官社学連携で、防災・減災の実質的なアクションにつながる機会にしてまいります。
②自治体と宗教施設・団体との災害時協力に関する調査
2019 年以来、5 年ぶりの調査であり、日本の防災における自治体と宗教施設・団体の取り組みの進捗を明らかにするものです。東日本大震災をはじめ多くの災害とコロナ禍を経験し、南海トラフ、首都直下型地震、頻発する水害への対応における連携を模索してきた成果は、どのようなものだったのでしょうか。今回の調査では、災害対策基本法に基づく緊急避難場所指定が 861 宗教施設、避難所指定が 385 宗教施設、災害対策基本法に基づかない一時滞在等に活用している宗教施設も 573 あり、基礎自治体と宗教施設の災害時協力の実態が明らかになりました。自治体と宗教施設の災害時協定に関しては、一度締結して短期間で無くなるケースは考えにくいので、令和元年調査で協定締結している自治体をいれると171となり、5 年間で 121 から 41.3%増加していることがわかりました。当日、詳細を報告いたします。
❖ 「未来共生災害救援マップ」(略称:災救マップ)とは
人間科学研究科と企業等の連携組織による「IT を用いた防災・見守り・観光に関する仕組みづくりの共同研究」(略称:防災見守り共同研究)(研究代表者:稲場圭信教授)では、この連携の動きをより社会的な力にすべく、地域資源と科学技術を導入した研究を進めてきました。2019 年には一般社団法人地域情報共創センターを設立し、大阪大学の知的財産である「災救マップ」の社会実装を進めています。
災救マップでは、寺社などの宗教施設と学校や公民館などの指定避難所を合わせ約30万施設を集約、インターネット上で公開しています。2024年春のリニューアルでは、高齢者等避難、避難指示などの発令の表示、ハザードマップの表示、道路や橋などの危険箇所の投稿・表示機能などを実装しました。

❖ 本件に関する問い合わせ先
大阪大学大学院人間科学研究科 教授 稲場 圭信(いなば けいしん)E-mail: inaba.keishin.hus@osaka-u.ac.jp
❖ 取材申し込みについて
12 月 19 日(木)午後 6 時までに、以下の内容を上記問い合わせ先あてにメールして頂きますよう、お願いいたします。
・氏名
・貴社名
・取材者人数
・テレビカメラの有無
・連絡先